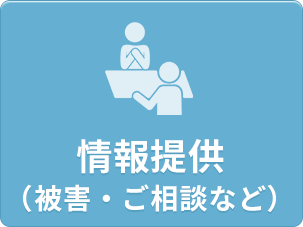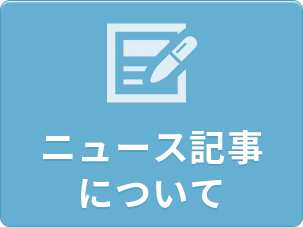SNS。(写真/Adobe Stock)
2024年12月に、献体を用いたトレーニングを海外で実施した際に、SNSに献体に関連する画像を投稿した美容医療関連の医師がいたことなどで大きな批判の声が集まった。倫理的な問題が指摘され、学会なども緊急に声明を発表する異例の対応を取った。
こうした背景の下、2025年2月に、東京大学や京都大学、東京都健康長寿医療センターの研究チームが、献体の生前登録者を対象とした全国初の調査を実施し、その結果を報告した。
今後、献体に関連する家族などへの情報提供の仕組みを整備する必要性も考えられそうだ。
「貢献」と「感謝」など恩返しの思い強い

調査を実施。画像はイメージ。(写真/Adobe Stock)
今回の研究では、自ら献体登録をした人を対象として、その動機などを調査するものだ。研究チームは、「ブレインバンク(死後脳のバンク)」への提供意思を登録した88人に対して郵送調査を実施し、52人から回答を得ている。平均年齢は79.5歳。女性が55.8%だった。
これによると、複数回答可能の回答の中で一番多く挙げられたのは、「疾患解明・未来の医療に貢献したい」が最多で、86.5%に上った。続いて「死後も役立ちたい」(82.7%)、「社会貢献への関心」(48.1%)などが続いた。医療への感謝、担当医や家族の勧めなどが自由記述から示された。
登録を決める際の情報源としては、パンフレットやガイドブックが安心感につながるようだった。
今後ほしい情報としては、家族の負担がかかる可能性があるので関連する情報がほしいという意見が挙がった。また、研究成果をかみ砕いて伝える情報も求められていた。
「継続的な情報提供」が求められる
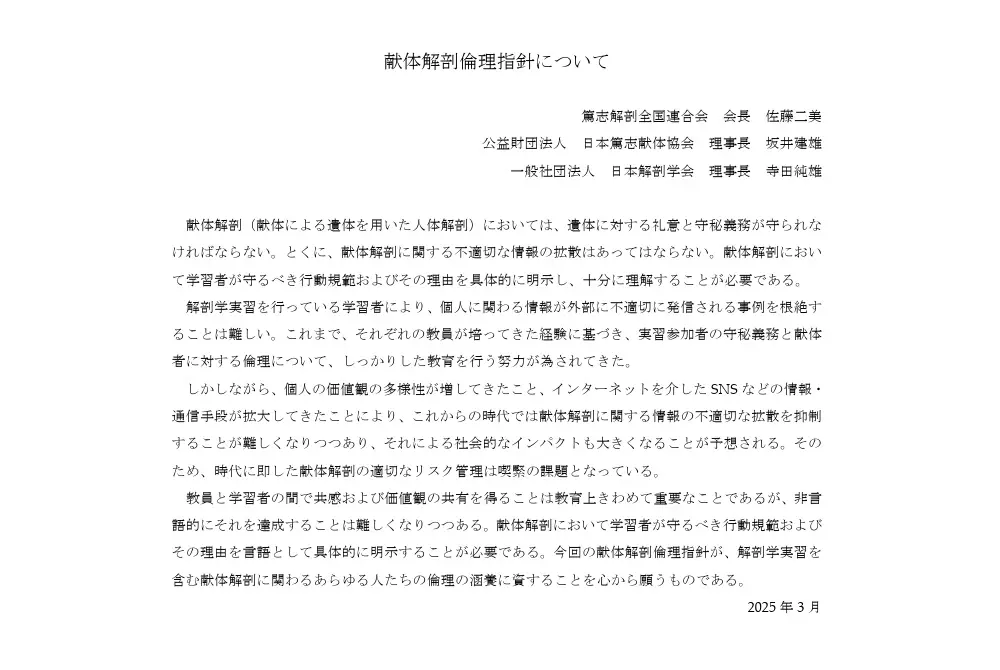
日本解剖学会、篤志解剖全国連合会、日本篤志献体協会が2025年3月31日、「献体解剖倫理指針」をまとめた。(出典/日本解剖学会)
研究では家族への情報の充実を求める意見も寄せられていた。自分自身の献体を提供した場合に、その献体がどのように扱われたのかを知りたいという考え方は当然の感情だ。
献体をめぐっては、海外での事例ではあるが、2024年12月に献体を用いたトレーニングが行われ、その画像がSNSで拡散され、強い非難の声を招いた。続いて、日本美容外科学会(JSAPSとJSAS)が声明を発表し、2025年3月には日本解剖学会、篤志解剖全国連合会、日本篤志献体協会が「献体解剖倫理指針」を公開した。
倫理指針の中では、医療従事者が献体解剖で得たことは、個人の秘密に該当するため、正当な理由なく第三者に伝えることは慎むよう求められている。
また、今回の研究では、研究者は次のようにコメントを寄せ、「遺体」や「死後」の話は研究倫理の文脈で議論されてきておらず、今後の課題と指摘している。
解剖や死後の研究参加の話は、年末の報道では⼤きな話題になりましたが、従来、社会的に注⽬を集めることは多くありません。世代をまたいで、患者・家族と医療者・研究者との共同作業で活動が積み重ねられていることや、今後も続けていくためにどのような取り組みが必要かを、引き続き考えていきます。これまで、研究倫理の⽂脈でも、「遺体」や「死後」の話はほとんど議論されてきませんでした。その⼈が⽣きていることを前提とした配慮・保護の議論の延⻑のみで、医学研究をカバーし切れるのか、わたしは問題意識を持ってきました。死後の研究参加は⼈や他者を信頼し、そこに託す視点が強くなります。この視点は、ブレインバンクに限らず、現在・将来の研究活動にとって⼤きな広がりがある概念だと考えています。
献体を用いたトレーニングは、日本国内でも行われている。しかし、こうした献体を扱う目的については情報提供が十分ではないとの指摘があり、今後は、情報提供を適切に行い、医学への貢献といった意義について丁寧に説明する努力が求められる。