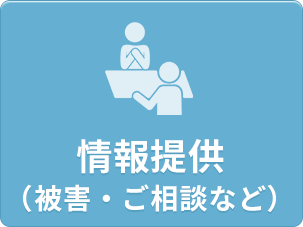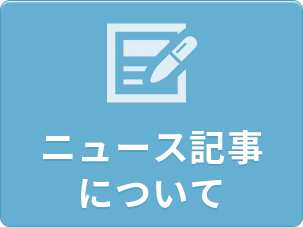研修会を開催した自由が丘クリニック理事長の古山登隆氏。(写真/編集部)
日本・台湾・中国の若手の医師が参加する研修会が、都内の美容クリニックで開催された。研究会には、台湾と中国からは約20人が参加。座学に加え、ヒアルロン酸やボツリヌス製剤の注入や糸リフト、HIFU(高強度焦点式超音波治療、ハイフ)照射がライブで実演され、それを直接見て学べる機会が設けられた。
自然な仕上がりを目指した施術をライブで示す

古山理事長自ら3LTBSTの考え方に沿い、午前にプラニングの実演を行い午後施術を行った。写真は糸リフトの施術を行っているところ。(写真/編集部)
- 開催概要→ 2025年4月に「自由が丘クリニックインターナショナルトレーニングコース」が開催され、日本、台湾、中国から若手医師約30人が参加。
- 主催と狙い→ 自由が丘クリニックとP.SKIN美容インスティテュートが共催。少人数制だからこそ密度の高い実践的教育を実施。形成外科の専門を持つ若手医師の技術力底上げを目指す。
- ライブ施術→ 研修の目玉はライブ施術で、自由が丘クリニックの古山登隆理事長自らプランニングから施術までを実演し、参加医師の理解を深めた。
2025年4月11日~12日の日程で開催されたのは「自由が丘クリニックインターナショナルトレーニングコース」と呼ばれる会。主催は、東京都目黒区の自由が丘クリニックと自由が丘アカデミーに加えて、台湾の美容医療機関であるP.SKIN美容インスティテュート。
研修会では、日本国内および台湾、中国から約30人の形成外科を専門とする若手医師を集め、自由が丘クリニック理事長の古山登隆氏をはじめ、同クリニックでの診療に関わる指導役の医師が美容施術の技術を伝えた。
ヒフコNEWSで古山氏は、規模を追わないクリニックであるからこそ「密度の濃い実践的教育もできる」と語っていたが、それを実践したのが、古山氏と台湾のピーター・ペン氏(P.SKINプロフェッショナルクリニックディレクター)。日本と台湾の参加者を集める形で2024年に始まったが、今年は中国の医師も加えた3つの地域からの参加者による会になった。古山氏は、「専門性を持つ若手医師の技術力底上げを目指している」と説明する。
初日は午前9時から午後6時まで、2日目は午前9時から午後1時まで途中休憩を挟みつつ、通しで行われた。
研修内容は、1日目の講義としては、ヒアルロン酸やボツリヌス製剤の注入、HIFUをはじめとした非外科的治療(ノンサージェリー)のほか、まぶたの手術や再生医療についての講義も行われた。
また、2日目の講義内容は、鼻の整形、スキンブースター(バイオスティミュレーター)、糸リフト、植毛についてだ。
1日目の午前の講義で、自由が丘クリニック理事長の古山氏は、自ら考案した「3LTBST」の考え方を示し、「顔のデザイン」について解説した。
ヒフコNEWSでのインタビューでも考え方が示されているが、3LTBSTとは、施術を行う上で、顔を構成している「3つのライン(3 Line)」「三角形(Triangle)」「バランス(Balance)」「肌のトーン(Skin Tone)」という4つの要素に着目するというアプローチだ。やり過ぎ感のない「Natural Looking(自然な仕上がり)」を目指すことが重要だと解説した。
研修会の大きな特徴は、先述の通り、ライブでの施術だった。
1日目のライブでは、古山理事長が自らヒアルロン酸やボツリヌス製剤の注入と糸リフトを実演した。3LTBSTの考え方に沿い、午前にプラニングの実演を。注入部位と糸リフトの挿入方法のプラニングについて、顔にマーカーを使って示しながら解説した。さらに午後に施術の実演をして、研修に参加した医師に実際に見てもらうことで、理解を促していた。
教授らが若手医師を直接指導

自由が丘クリニック形成外科部長の古山恵理氏がHIFUの施術の計画から実施までの過程を実演。(写真/編集部)
- HIFUのライブ施術→ 自由が丘クリニックの古山恵理氏がHIFU施術を実演し、東海大学の河野太郎教授が前額部の安全性について具体的な注意点を解説。
- 国際的な交流→ 台湾・中国の医師が積極的に参加し、アジア全体での美容医療の教育と技術共有が広がる兆しを見せた。
一方で、同じく1日目に行われたHIFUのライブでは、自由が丘クリニック形成外科部長の古山恵理氏が施術の計画から実施までの過程を実演して見せた。
この際に、東海大学形成外科教授の河野太郎氏が、施術の安全性を確保するために気を付けるべきポイントを解説した。例えば、前額部は、皮膚が薄いことから、HIFUの設定を4.5mmにすると、骨に反射して意図せぬ場所に熱が加わる可能性があると、画像を見ながら説明した。
この実演の前段として1日目の講義では、東海大学形成外科教授の河野太郎氏が、HIFUのトラブルの実際について自ら関わった調査に基づいて解説していた。ここで述べた注意点をライブ施術にも組み込みつつ、実践の中で理解しやすくなるよう工夫していた。
また、東京リライフクリニック総院長の石川正志氏が再生医療について解説。同クリニックでは、再生医療の臨床研究に力を入れてデータ蓄積に力を入れている方針を説明した。
帝京大学形成・口腔顎顔面外科学講座主任教授の小室裕造氏は上まぶたのたるみ治療について、また、自由が丘アカデミー代表理事で、自由が丘クリニック眼瞼下垂外来主任である大慈弥裕之氏は上まぶたの治療について講義をした。まぶたの解剖学的な構造を示しながら、施術の考え方と手法を解説した。
自由が丘クリニック院長の秋本峰克氏は、顔の解剖学の詳細を血管の位置や走り方を示しながら図解した。
さらに2日目の講義では、自由が丘クリニック総院長の中北信昭氏が鼻の手術に関して解説。北里大学名誉教授である武田啓氏が植毛について解説した。また、糸リフトに用いられるスレッドを開発した台湾のアーロン・シエ氏が、糸リフトやバイオスティミュレーターについて解説し、自由が丘クリニック副院長の兵頭徹也氏が糸リフトのライブを行った。
台湾のピーター・ペン氏は、若手医師の高い関心を受けて、「台湾、中国の若手医師にとって実践的な内容で、講義もライブ施術のいずれも参考になった。来年はさらに規模も大きくなりそうだ」と感想を述べていた。中国からの初参加者は研修を貴重な学びの場として受け止めていた。
西洋とは異なる、東洋人に適した美容医療の追求を背景に、今後はアジア諸国の医師同士の交流が一層活発になることが予想される。