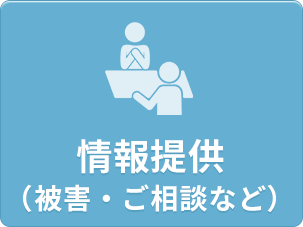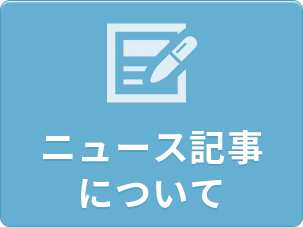尾見徳弥(おみ・とくや)氏。クイーンズスクエアメディカルセンターセンター長/日本医科大学客員教授/東京医科大学客員教授(写真/編集部)
尾見徳弥(おみ・とくや)氏
クイーンズスクエアメディカルセンターセンター長/日本医科大学客員教授/東京医科大学客員教授
──医学部卒業後の2年間初期研修を経て直接美容医療に入る「直美」が問題になっている。国は保険診療の経験がなければクリニックの管理者になれないルールを作り、直美の対策を打とうとしている。
尾見氏: 美容医療はほとんどが自由診療で、保険診療の仕組みから外れているため、国が保険診療のルールを厳しくしても影響が及びにくい面があります。
実質的に美容一本で運営しているクリニックには大きな影響が及ばない可能性があり、そこが今後の課題でしょう。
──美容医療の安全面が不安視されるようになっている。
尾見氏: 未熟な医師がいきなり難易度の高い施術を行っているという話を聞きますが、本来なら麻酔の管理や合併症のリスク、術後のケアまで考えると相応の知識と経験が必要です。ところが、それを怠ったまま、大勢の人々を集めて利益を上げる構造になると、安全が脅かされます。実際、手術後の後遺症が出ても適切なケアをされないケースも報告されています。
それでは「悪貨が良貨を駆逐する」状態になりかねません。真っ当なクリニックほど人材や設備にコストをかけていると思いますが、悪質なクリニックに人が流れ、まともなクリニックが経営的に不利になるのは問題だと考えます。
──国や行政がルールづくりを進めている。
尾見氏: そうですね。国や行政が主導して、しっかりとしたルールを作る必要があります。
例えば、再生医療でも、委員会に計画書を提出して認められれば治療ができますが、実態として効果や安全性のエビデンスが不透明なまま行われている治療が少なくない状況があります。
日本の場合は法制度が通達ベースで動く部分が大きいことや、官庁の人事異動のたびに方針が変わりやすいこともあって、制度設計が不十分であると感じることがあります。
一方で、美容業界の中でルールを作れるかといえば、美容医療の分野には利害関係者が集まり、それぞれ置かれた立場が異なるので、意見を集約するのが難しいという実情もあります。
──施術を希望する人の立場からすれば、どのクリニックを選べばいいか分かりにくい。
尾見氏: 総じて、美容医療には大きな可能性がある一方で、ルールが整っていないせいでトラブルや混乱を招いている部分があると感じています。
今は若い世代の方がSNSなどで簡単に情報に触れられるようになり、美容医療に興味を持つ人が増えています。そういった方たちを守ることが求められると思います。
──2025年、業界ガイドラインが作られる見通しであるのは良い動きとなる。
尾見氏: 厚労省や日本美容医療協会、美容関連学会などが協力して、業界ガイドラインを作る予定になったのは良いことですね。
その議論が進む中で、「美容と医療の線引きをどうするのか」「安心して施術を受けるにはどうすべきか」という議論は、今後さらに大きくなっていくでしょう。さまざまな部分でのルールを定めなければ、悪質なクリニックがはびこり、美容医療全体の質が低下する恐れがあります。
──これからの美容医療の展望は?
尾見氏: 美容医療以前の問題として、まずは「正しい診断」が非常に重要だと考えています。シミやイボに見える病変が、実は悪性腫瘍だったり、アトピーやニキビ肌の患者さんに間違った施術をしたりすると悪化してしまうこともあります。そこを見分ける力は、医学教育と臨床経験を積むことで培われるものです。ここをないがしろにしたまま、美容医療を手掛けることは、本来の医療の役割を果たしていないと思います。
国や業界団体、学会などが連携しながら、安心できる環境を作っていく必要があります。そうした協力が美容医療の最重要課題だと思います。(終わり)