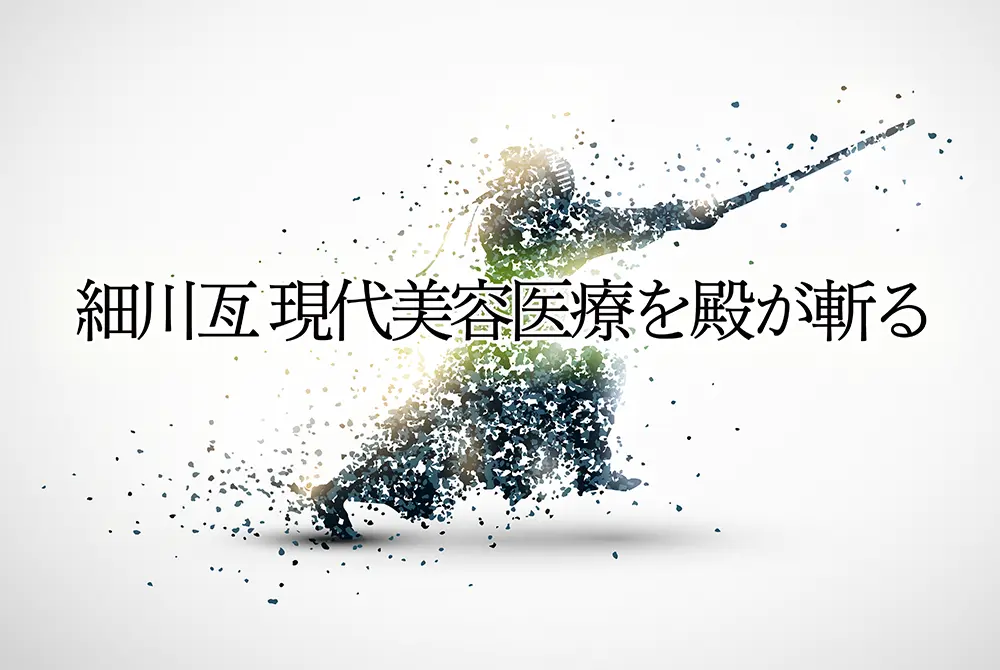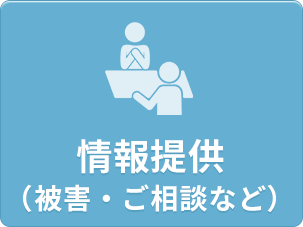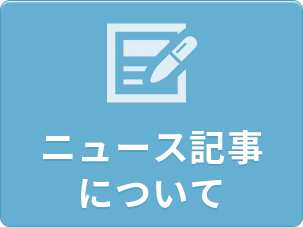「細川亙 現代美容医療を殿が斬る」では、日本形成外科学会理事長をはじめ、多くの要職を歴任し、米国形成外科学会名誉会員でもある細川亙氏が、現代美容医療が抱える様々な問題に鋭い視点で問題提起する。「殿」というのは、細川氏が細川ガラシャの子孫であるから。その源流は明智光秀に通じる。そんな歴史的背景を持つ細川氏が現代に舞台を移して美容医療の分野で一刀を振るう。激動の美容医療の世界をどう治めるのか。
第5回テーマ「東京都も警戒している美容医療の闇」
美容クリニックの引き起こす問題に対して国は警戒の姿勢を強めている。そうした中で、東京都も医療監視業務の研修テーマとして美容医療を取り上げ、現場の職員が美容医療の状況について積極的に情報収集している。細川氏は、国や地方自治体の行政にとって、美容医療が監視すべきターゲットとして注目されているという。一般の人たちが美容医療の恥部を正しく理解する重要性について指摘する。
美容医療が行政の監視対象に
東京千代田区九段北にある特別区職員研修所というところで講義(レクチャー)を行ってきた。対象は東京都23区で医療監視業務に従事する特別区職員で、1月21日に行われた専門研修テーマは「医療監視」、そして私の講義の題は「美容医療の現状について」だった。私以外の講義は「衛生検査所の監視指導のポイントについて」、「医療法人設立時の書類審査のポイントと設立後の諸手続き」、「医療広告ガイドラインの読み解き方」であり、それぞれ医師、行政官、弁護士による講義である。
私の講義は美容医療そのものに関するものであるが、医療広告ガイドラインに関する山田瞳弁護士の講義も美容医療に深くかかわる内容であったと推察される。というのは、医療広告として一般の都民が目にする広告のほとんどは美容医療広告だからである。つまり都の特別区職員に対する医療監視という専門研修テーマ4つの講義の中で少なくとも2つが美容医療関係の内容であったことになる。耳鼻科や呼吸器内科や小児科や整形外科のような一部の診療科のみをターゲットにした医療監視などは格別行われていないことを思うと、美容医療という世界が、行政の立場から格別に問題のある(監視すべき)分野として扱われていることがわかる。
厚労省が出した異例の警告文書の真意
美容医療の問題は、医療レベル面と商道徳面の双方でみられる。前者すなわち医療レベル的な問題は、「直美」問題にも現れているように経験不足の美容医療医が激増して事故を引き起こしているのであるが、一方後者の商道徳的な問題というのは、消費者庁が注視している問題である。例えば、低価格で施術を行っているかのような医療広告を流して来院者を集め、実際には高い料金の施術を押し付けるようなことをしている医療施設が少なからず存在する。○○円ポッキリというような触れ込みで客を呼び込んで高い料金を吹っ掛ける“ぼったくりバー”と同じ手法である。
数年前に厚生労働省は消費者庁や国民生活センターとともに、「美容医療を受ける前にもう一度」という国民への警告文書を発出した。「眼科医療を受ける前にもう一度」などという注意喚起は見たことがない。美容医療に対してだけこのような警告文書が出されたのである。美容医療のクリニックの門をくぐるときには、特殊詐欺やぼったくりバーに対すると同様なレベルの警戒を払いましょうというのが、国からの警告文書の真意である。
自分が住んでいる美容医療界に大変荒んだ部分があることは悲しいが、悲しんでいるだけではこれからも被害者が増え続けるに違いない。だから私は美容医療界の恥部を今後絶え間なく情報発信し、それによりこの業界に所属する人たちによる浄化作業が進むことを期待したい。しかし、業界側の自覚だけではなかなか改善は望みがたいので、消費者側もこの情報発信を真剣に受け止め、自らが被害を受けないようにする姿勢を持たないといけない。特殊詐欺被害に遭わないように、ぼったくりバーに入らないようにする注意を払ってほしいのである。