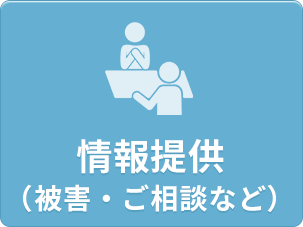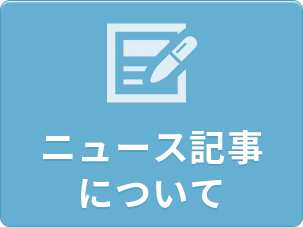美容クリニックの院長に求められる資格とは。画像はイメージ。(写真/Adobe Stock)
これは1年後の話だが、国内の多くの医療機関では「管理者」の資格が重要になる。
一般的にこのルールは美容クリニックにはあまり関係ないとされているが、美容クリニックを利用する人が「管理者」を基準にクリニックを選ぶ可能性もあり得ると考えている。
保険診療の院長は「5年間の保険診療の経験」必要に

保険診療を提供する医療機関の管理者に必要な経験。画像はイメージ。(写真/Adobe Stock)
- 直美問題の背景→ 初期研修後すぐに美容医療へ進む若手医師(直美)が増加し、対策の必要性が指摘された。
- 管理者資格の新ルール→ 保険診療を行う医療機関の管理者(院長)になるには、初期研修2年+保険診療経験3年の計5年が必要となる方向で調整。
- 美容医療への影響→ 美容医療の多くが自由診療であるため、今回の管理者ルールが直美問題に直接的な影響を与えるかは不透明。
そもそも医療機関の管理者が注目された背景には、美容医療の「直美」の問題がある。
「直美」とは、医学部を卒業後、2年間の初期研修を終えた直後、すぐに美容医療に進むこと。このような若手医師が増え、医学部2校分ほどに増えていることから、対策の必要性が指摘されていた。
この問題が大きく取り上げられたのは、2024年に厚生労働省が開催した「美容医療の適切な実施に関する検討会」。同検討会では、美容医療の「安全」と「質」を向上させるための施策が検討された。しかし、直美に関しては、医師の地域や診療科の偏在問題と見なされ、その後は「医師偏在対策推進本部」による課題対策に委ねられることになった。
その後、「直美」への対策の一環として、保険診療(病気などを健康保険を使って診てもらう医療)の医療機関の管理者になるためには、2年間の初期研修と、3年間の保険診療経験が必要となる仕組みが導入される方向になった。これは、医療提供などのルールを定める医療法の改正により、管理者の役割が明確化されるものとなる。一般に管理者とは院長を指すが、保険診療を行う医療機関の院長になろうとする場合、通算で5年間の保険診療経験を積むことが求められる。国内にある医療機関は多くが保険診療を提供しており、その院長になるには、初期研修を終えた後に、何かの専門医を取得するなど修練が必要とされる形になる。これは直美対策のためにできたルールと見なされている。
一方で、この仕組みは直美への対策と直接結びつくわけではないという指摘もある。というのも、美容クリニックの中には保険診療を提供しているケースもあるが、直美が主として問題視されるのは自由診療(健康保険を使わずに自費で診てもらう医療)の領域だからだ。保険診療を提供する医療機関を対象とした今回のルールが、そのまま直美に関連する自由診療に適用されないと見られている。
そうした中で、2025年2月14日に医療法改正案が閣議決定された。この法案では、一般的に院長である管理者の役割が明確にされ、ここまで示したように保険診療の医療機関の管理者になるには5年間の保険診療経験が必要とされる方向だ。今後、衆議院で議論が進むことになる。
美容クリニックの信頼性を示す根拠になる可能性

美容クリニックを選ぶときの参考情報。画像はイメージ。(写真/Adobe Stock)
- 管理者ルールの影響→ 「管理者の資格を持つ院長」と「持たない院長」が生まれる可能性があり、美容クリニックに影響を与える可能性がある。
- 専門医資格との比較→ 現在も美容クリニックでは専門医資格が信頼性の指標とされており、管理者資格も同様に参考情報として活用される可能性がある。
- 今後の展望→ 2026年4月から新ルールが適用される見通しであり、医師が取得できる資格の一つとして注目される可能性がある。
果たして管理者のルールは、美容クリニックに本当に影響を与えないだろうか。
確かなことは言えないが、影響を及ぼさないとは言い切れない。
というのも、美容クリニックの中に、今後「管理者の資格を持った院長」と、「持たない院長」が生まれる可能性があり、これが気にされる可能性が否定できないからだ。
実際、現在も、多くの美容クリニックでは、専門医資格の有無を医院のウェブサイトで示し、信頼性を裏付ける根拠の一つとして参考にされている。専門医資格がなくても、美容クリニックの院長を務めることは可能であり、こうした関係性は今後、管理者の資格とも近いと考えられる。美容クリニックを利用する人にとっては、院長に管理者の資格があるならば、参考情報として活用される可能性がある。
管理者の新しいルールが適用されるのは2026年4月からと先の話になる見通しだが、将来的には医師が得られる資格の一つとして注目しておいてもよいかもしれない。