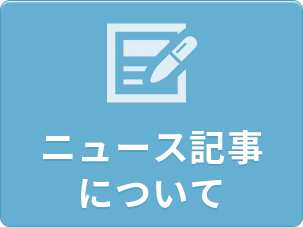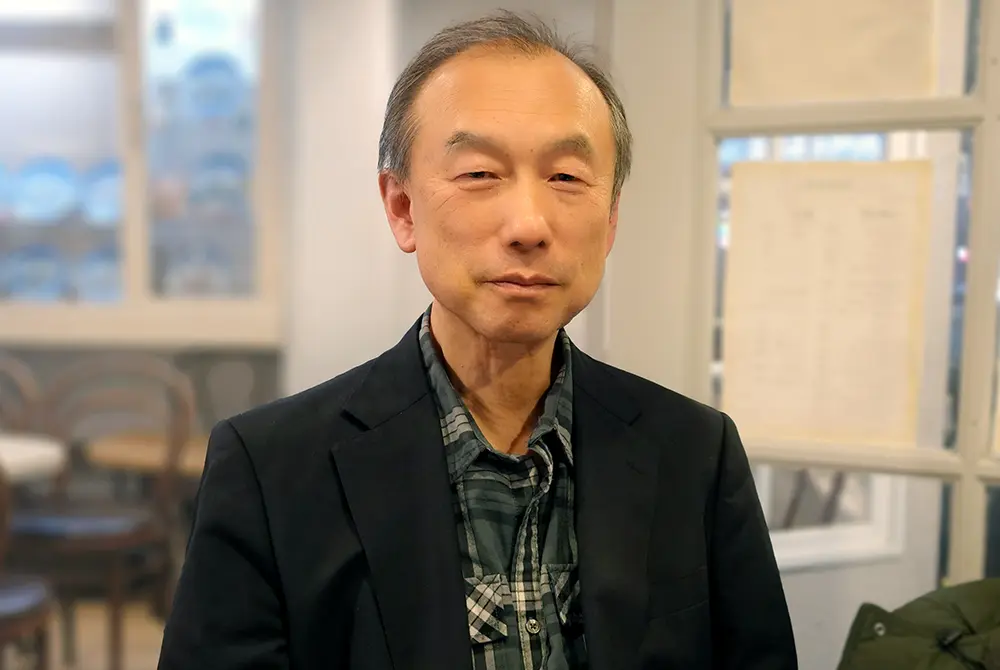
小川敦生(おがわ・あつお)氏。多摩美術大学芸術学科教授/美術ジャーナリスト。(写真/編集部)
小川敦生(おがわ・あつお)氏
多摩美術大学芸術学科教授/美術ジャーナリスト
──江戸時代の浮世絵、とりわけ美人画には「絵師による理想化」が少なからずあった。
小川氏: 喜多川歌麿の美人画を見てみると、当時の実在の女性をモデルにしているはずなのに、どこか皆似ています。面長の輪郭と涼しげな目元。これが歌麿の描く美女の類型であると言われています。もちろん、現実のその女性そのままではなく、より洗練された顔立ちに加工されていたのが特徴です。
一方で、幕末から明治初期に活躍した画家である高橋由一が西洋の技法として修得した油絵で花魁を描いたときは、あまりにもリアルでモデル本人が「もっと美しく描いてほしかった」と泣いてしまったという逸話もある。つまり、肖像画において人々が求めるのはありのままではなく、理想化された姿だったわけです。

高橋由一『花魁』。1872年の油彩画。(Public Domain)
──写真のレタッチやフィルター加工などで同じような構図がある。
小川氏: 浮世絵の類型化された美女像を見て、「こういう鼻筋の通った女性が美人なんだ」「こういう髪結いがモテるんだ」と感じる。すると町の女性たちは、多少なりとも「近づきたい」と思う。それを叶えるために、化粧品を使ったり、髪型を工夫したり、衣装を真似したりするわけです。
江戸の町は、そうした「理想像を真似てみる」循環が既に存在していたと推察されます。今の私たちがSNSで「映え」を追求したり、美容医療で気になる部分を整えようとしたりするのと構造はほとんど変わらないんですよね。
江戸の庶民は、美人画の奥にある花魁の哀歓や苦境や歌舞伎役者が背負うドラマを想像し、そこに強い魅力を感じました。現代では、この物語の共有がSNSを通して一気に加速しています。タレントの過去や日常、努力の過程が推し活によって可視化され、ファンはその物語にどっぷり入り込む。そして「もっと応援したい。もっと近づきたい」という気持ちを強くする。
そこに映えるための競争が加わり、「私もあの人のように可愛くなりたい」「同じコスメを使えば自分もあの推しのように近づける」といった行動が、まるで江戸時代の「町娘が美人画を真似する」状況と重なってきます。

喜多川歌麿『江戸の花 娘浄瑠璃』 (Public Domain)
──時代によって美しさの基準はコロコロ変わる。
小川氏: 簡単に言えば、「人間は外部からの情報や物語を通じて、感覚が開いていく」からだと思います。自分の中に全くなかった感覚も、ある映画やアイドルとの出会いでがらっと変わってしまうように、江戸時代もまた、浮世絵というメディアを通じて「これが粋なんだ」「これが花魁のような美しさだ」といった価値観を共有していました。
しかも、受け手が増え、批評や会話、評論が盛んになればなるほど、その基準は再び新しい段階に押し上げられていく。これは循環構造ですね。一度定着した理想像はまた別の理想像に塗り替えられ、あるいは多様化の方向に進むこともある。私たちは「今の基準こそが唯一の正解」と考えずに、常に相対的に見直すことが大事なのではないでしょうか。
──江戸時代と比較すると、技術の進歩や情報拡散力が加速している。
小川氏: 一つは、「美しさが商品化されている事実」を意識することでしょう。江戸時代の浮世絵も、版元や絵師にとってはビジネスでした。蔦重のような出版人は、それこそ商売っ気たっぷりに「どうすれば売れるか」を考え、美人画を大量に流通させていました。
現代でも、SNSでバズる写真や映像、美容整形やコスメも含めて、ビジネスとしての構造があります。お金をかければいくらでも美しく見せられる仕組みがあり、それを求める側の欲望も尽きない。そうした商業的なからくりを知ったうえで、いかに美を追求するのか、どれくらい距離を保つのかを判断することが大事だと思います。
──江戸時代から私たちは学ぶことができる。
小川氏: 人々が求める「美への憧れ」は時代を超えて普遍的です。それが浮世絵だったのか、テレビだったのか、SNSだったのか。メディアが変わるたびに私たちの美しさの基準や味わい方も変容してきました。
蔦重の時代、江戸の人々はまだテレビも映画も知らないけれど、浮世絵を通じて十分に夢中になり、自分たちなりの「アイドル文化」を楽しんでいたわけです。
その構図を知ると、「今の私たちも、結局は同じことをやっているのかもしれない」と気づくことができます。美しいものを追いかけ、憧れの人や物語にのめり込み、そのためにお金や時間を費やす。そこには常に商業的仕掛けがあり、メディアの特性があり、そして私たちはそれを楽しみながら生きている。この歴史の連続性を理解することで、もしかすると「今どきのアイドル追っかけやSNSの映え文化は、江戸時代の庶民の美人画ブームと何ら変わらないのだ」と気づくかもしれません。
そこから、「自分が追求する美しさ」や「社会が押し付けてくる美の基準」と、どう向き合えばいいのかを見直すきっかけになれば興味深いかもしれません。(終わり)